採用コラム
Column障害福祉サービス受給者証の取得方法と受けられるサービス
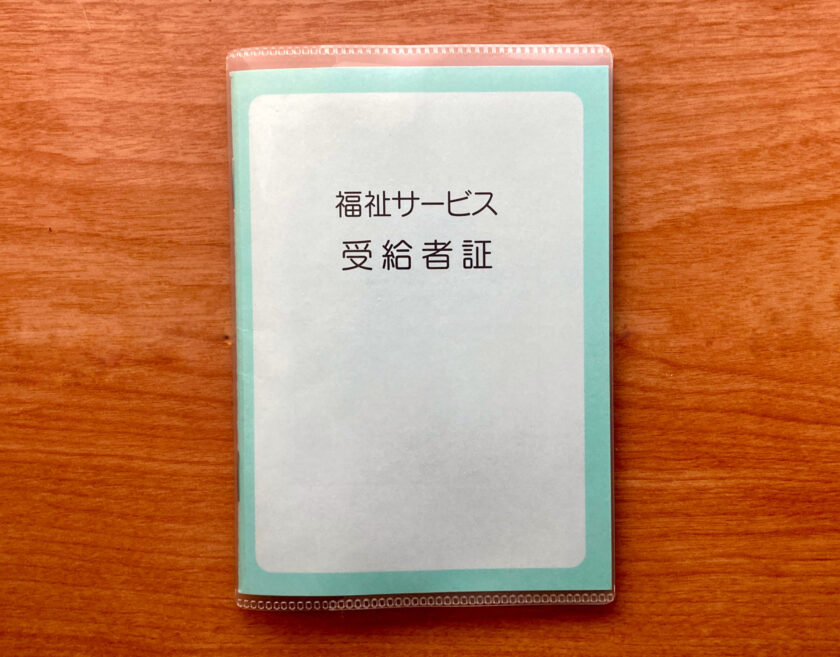
障害があることで仕事や生活に不便を感じることはありませんか?
そんな時、「サービスを受けたい」と行政に申請することで発行されるのが「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」です。受給者証は福祉サービスを円滑に受けるためには必要不可欠な証明書です。
本コラムでは、
「受給者証を発行したいけど、取得方法が分からない」
「受給者証を手にしたらどんなサービスが受けられるの」
といった悩みを解決するために、取得方法から利用できるサービスまでをご紹介します。
ぜひ、参考にしてみてください。
障害福祉サービス受給者証とは
障害福祉サービス受給者証(受給者証)は、障害や病気により仕事や日常生活に困難を感じる方が、行政に申請して発行してもらう証明書です。これにより、障害福祉サービスをスムーズに受けられます。この受給者証があれば、「介護給付」と「訓練等給付」などの福祉サービスを利用でき、障害のある方が地域で尊厳をもって生活できるよう支援を受けられます。障害者手帳とは異なるため注意が必要です。
受給者証の役割
受給者証は、利用者が希望する事業所からサービスを受けるための証明です。受給者証には10桁の受給者証番号や障害の種別、交付年月日などが明記されており、これによって利用者がどのような支援を必要としているかが示されます。
受給者証の取得方法
受給者証を取得するには、いくつかのステップを踏む必要があります。
①相談・申し込み: まず、お住まいの自治体の障害保険福祉課などに相談し、必要な書類をもらって相談支援事業所に申し込みます。障害者手帳や診断書、自立支援医療受給者証があると手続きがスムーズに進みます。
②サービス等利用計画案の提出: 市役所で選ばれた相談支援専門員と一緒に、どのようなサービスを利用したいか、具体的な支援内容などを盛り込んだ「サービス等利用計画案」を作成し、市町村に提出します。
③訪問(聞き取り)調査: 日常生活の様子や困っていることなどを質問形式で答える聞き取り調査を受けます。この調査で障害支援区分が決定され、区分が高いほど受けられるサービスが増えるため、ありのままを伝えることが大切です。
④支給決定: サービス等利用計画案を提出後、市町村からの支給決定を待ちます。決定までには即日から2ヶ月ほどかかる場合があります。
有効期限と更新
受給者証にはサービスごとに有効期限が定められています。期限が切れてもすぐに給付が止まるわけではありませんが、引き続きサービスを受けたい場合は更新手続きが必要です。更新月の2〜3ヶ月前には役所から案内が届くので、忘れずに確認しましょう。
受けられるサービス
受給者証を取得すると、以下の「介護給付」と「訓練等給付」の様々なサービスを利用できます。
①介護給付
主に日常生活のサポートに関するサービスです。
・居宅介護: 食事や入浴、排せつなどの身体介護、調理や洗濯、掃除などの家事援助、通院時の付き添いなど。
・重度訪問介護: 重度の肢体不自由者などが対象で、身体介護、家事援助に加え、外出時の移動支援や入院中の支援も。
・同行援護: 視覚障害者の方が外出する際の危険回避や代筆、代読などの支援。
・行動援護: 知的または精神障害者で行動に常に介護が必要な方への、行動時の危険回避や外出時の介護。
・重度障害者等包括支援: 重度の障害があり、意思疎通が困難な方が対象で、複数のサービスを包括的に利用できます。
・短期入所(ショートステイ): 介護者が不在の場合に、一時的に障害者支援施設などに宿泊して介護を受けるサービス。
・療養介護: 医療機関に長期入院している方が、医療と合わせて介護や日常生活の支援を受けるサービス。
・生活介護: 常に介護が必要な方が、身体介護や家事援助、創作活動や生産活動、生活能力向上のための支援を受けるサービス。
・施設入所支援: 夜間も支援が必要な方が、居住場所の提供や身体介護、食事提供、健康管理などを受けるサービス。
②訓練等給付
自立した生活や就労を目指すためのサービスです。
・自立生活援助: 一人暮らしで不安がある方が、定期的な訪問により食事や洗濯、金銭管理、健康状態などの支援を受けるサービス。
・共同生活援助(グループホーム): 共同生活をしながら生活上の支援を受けるサービス。支援区分がなくても利用できます。
・自立訓練(機能訓練): 身体障害者などが生活能力の維持・向上のため、リハビリテーションなどを受けるサービス。
・自立訓練(生活訓練): 入浴、排せつ、食事など自立した生活に必要な訓練や、地域で生活するための相談援助。
・就労移行支援: 一般就労を目指す障害のある方が、職場体験や就労に必要な知識・スキル向上の訓練、就職活動・定着支援を受けるサービス。
・就労継続支援A型: 雇用契約に基づき就労できる障害者の方への、生産活動の機会提供や就労スキル向上の訓練。最低賃金以上の賃金が保証されます。
・就労継続支援B型: 雇用契約なしで、生産活動の機会提供や就労スキルアップを行うサービス。賃金は工賃や成果報酬が主です。
・就労定着支援: 就職後6ヶ月以上経過した方が、仕事を継続できるよう不安や問題に対して相談や助言を受けるサービス。
まとめ
障害福祉サービス受給者証は、障害のある方が多様な福祉サービスを利用するために不可欠なものです。取得方法や利用できるサービスを理解し、必要であれば自治体の窓口に相談してみましょう。
